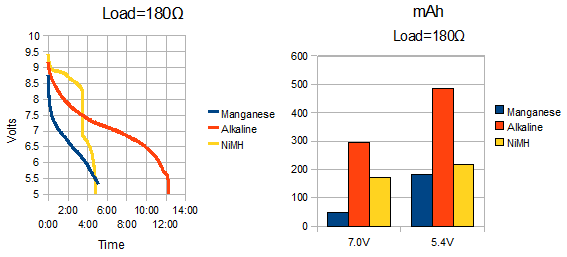6LF22は角型セル、6LR61は円筒セルです。
| 一般名称 | JIS型式 | 一次/二次 | 公称電圧 | 正極 | 負極 | 電解液 | 備考 |
| マンガン電池 | 6F22 | 一次 | 9.0V | 二酸化マンガン(MnO2) | 亜鉛(Zn) | 塩化亜鉛(ZnCl) | 積層 x6 |
| アルカリ電池 | 6LF22 | 一次 | 9.0V | 二酸化マンガン(MnO2) | 亜鉛(Zn) | 水酸化カリウム(KOH) | 積層 x6 |
| アルカリ電池 | 6LR61 | 一次 | 9.0V | 二酸化マンガン(MnO2) | 亜鉛(Zn) | 水酸化カリウム(KOH) | LR61(単6) x6 |
| リチウム電池 | - | 一次 | 9.0V | 二硫化鉄(FeS2) | リチウム(Li) | 有機電解液 | SONNENSCHEIN LITHIUM社 SLM9V=1200mAH |
| ニッカド電池 | - | 二次 | 7.2V | オキシ水酸化ニッケル(NiOOH) | カドミウム(Cd) | 水酸化カリウム(KOH) | 6セル |
| ニッケル水素電池 | - | 二次 | 7.2V | オキシ水酸化ニッケル(NiOOH) | 水素吸蔵合金(MH) | 水酸化カリウム(KOH) | 6セル GP30R7H=300mAH |
| ニッケル水素電池 | - | 二次 | 8.4V | オキシ水酸化ニッケル(NiOOH) | 水素吸蔵合金(MH) | 水酸化カリウム(KOH) | 7セル GP20H8H=200mAH |